
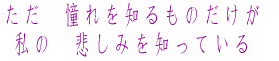
 |
ガリ版印刷の 同人誌 狼群 33号です。 僕の本棚には 学生時代に作った ガリ版刷りの 同人誌 20冊ほどと 当時のビラ数枚が 棄てられずに 残してあります。 あの時代に 活字になれなかった 僕の散文たちを やっと 活字にして あげることができました。 さとちゃん |
古い哥〔うた〕 佐藤 さと
出逢い
五月の下旬は雨が、生ぬるい雨が降り続く。
下宿ではきっと島さんが
憂鬱そうにこの雨を眺めているに違いない。
「僕がこの下宿に入った時、
この裸電球は四十燭光だったんだぜ。
あまりにも 暗すぎるので
本も読めなかったんだ。
だから、下宿に入って一番最初に
買った物は
インスタントラーメンよりも先に
六十燭光の電球だった。」
島さんは苦笑いしながら
天井からつりさげられている
灰色のガラス玉を左右に揺らした。
「ひとりで淋しくないの?」
と聞くと
「家にいるよりは、淋しくなんかないさ。」
と応えてくれた。
僕が初めて島さんの下宿を訪ねた時
島さんは
畳の上で腹這いになって
原稿用紙に文字を埋めていた。
そして
臆病そうに
一枚の原稿用紙を僕に差し出した。
「花が燃える」 島
僕の心を知るものは 花
花が美しいのは
生きたい生きたいという
ひたむきな心があるからです。
僕の心に
花が咲いた時
僕はその花を
犯さねばならない・・・・・。
走り書き。
極太の万年筆で書かれた黒い文字が
妙に女々しく見えた。
「島さんの書いた 花 という文字は
死 という文字に よく似て います。」
一年生の僕には、それだけしか
いえなかった。
島さんは なにも言わず
仰向けになって寝ころがったまま
ハイライトを
吸っていた。
蛇の目傘
大学も三年目になると
雨が降る日には僕は大学に行かない
ことが習慣になっていた。
島さんは
晴れた日にも
雨の日にも大学には来なかった。
僕の家には
蛇の目傘が一本ある。
去年の大学祭の時
島さんが 翌日配るビラのガリ切りをするために
島さんの下宿に泊り込んだ。
その時のお礼に
蛇の目傘をもらった。
蛇の目傘は
開くと独特の油っぽい匂いがした。
そんな蛇の目傘を取り出し
僕はあてもなく家から
外に出かけた。
雨が五日も続くと
道路には餌を食えなかった
雀が一羽二羽と
固くなって死んでいた。
僕が優雅に
散歩をしている間にも
か弱い小鳥は死んでしまうのだった。
羽毛が憐れにも雨粒を弾き
固く閉じられた灰色の
瞼の上には泥が付いていた。
ーかわいそうに・・・・−
僕は雀を拾い
叢の土をほじくって埋めた。
ーこの雀は、生きている間に
一体 何を見たのだろうか?−
昔話
島さんは七回生である。
僕が入学した時には五回生で
文藝部の部長をしていた。
島さんは僕に昔話をよくしてくれた。
二回生の時に学費値上げ反対ストをやり
危うく処分されるところだったとか
三里塚闘争で
機動隊に挟み撃ちにあい
必死で逃げてきたとか・・・・・。
最後は、ハイライトの煙を
空しく吐き出して
「また、昔の話になってしまったな。
君は君の一番やりたいことを
すれば いいんだよ。」
と結んだ。
ーやりたいこと。・・・ー
僕は二年間にやりたいことはなにもやれなかった。
そして今もやりたいことは何もない。
やらねばならないことさえ
僕にはできなくなっていた。
僕にできること。
それは
自分を慰撫すること。
誰にも触れられたくない傷口を
舐めまわすことしかできなかった。
いつも
ふわふわ
揺れ動いている。
ーあらゆる芸術活動は、所詮
経済機構から出た
屁のようなものだ。−
と
太宰の言った言葉が
今、僕の
傷口に
かさぶたを被ったようです。
哥〔うた〕
昨日、島さんの下宿に遊びに行ってきた。
雨宿りのつもりだった。
リンゴ箱二つ並べた机を挟み
色白の女の人と一緒にお茶を飲んでいた。
「こんにちは。」
「おう、おまえか。よく、来た。まあ、座れ。」
ひどく明るい笑顔で迎えてくれた。
「ええ、でも、女の人が・・・・」
島さんが、女の人の顔を窺うと、女の人は微笑して
「どうぞ。」
と声をかけてくれた。
ーやさしそうな ひとだ。−
僕は信じた。
昨夜は遅くまで、レッドのダブルサイズを
三人で空にするまで
飲んでいた。
そして 最後の一杯を島さんが飲みほすと
涸れた声で
インターを歌いだした。
ー僕は、いざ、闘わん、いざ、奮い立て、いざ、・・・・
という さわりの歌詞しか知らなかった。
島さんは二番まで歌って
「何にも、いいことなど、ありは しねぇ。」
と叫び
倒れてそのまま眠ってしまった。
女の人は
寝てしまった島さんの身体の上に
慣れた仕草で押し入れから取り出した
毛布をかぶせた。
「バス停まで、送るわ。」
女の人が僕に言った。
僕は女の人の差す傘にはいり、
バス停までフラフラ歩いていった。
「いまどき学生運動をする人は、
よっぽど、すね者ね。」
泣きそうな声で女の人が言った。
「でも、僕等には、それが、できないのです。」
ー歌を忘れたカナリアよりは
鳴いて血を吐くホトトギスー
島さんのいつもの口癖だった。
〔終わり〕
〔二十歳〕
|
次頁へ |

